2025年末に開催されたレペゼンの解散ライブ。SNSでは「PayPayドームがガラガラ」「大赤字では?」といった声が飛び交いました。
しかし、実際のチケット販売数や経費を冷静に見ていくと、単純な“失敗”という言葉では片づけられない構造が浮かび上がります。
この記事では、レペゼンのドーム公演の損失の実態、2.5万枚と言われるチケット販売数の真偽、そして「赤字ライブ」が意味するものを多角的に掘り下げます。
- レペゼン解散ライブが「赤字前提」で行われた理由
- チケット販売数と実際の動員数に生じたギャップの真相
- “ガラガラ”報道の裏にある感情と象徴の構造
レペゼン解散ライブは本当に赤字だったのか?損失構造を読み解く
レペゼンの解散ライブは、「PayPayドームがスカスカ」「大赤字確定」とSNSで拡散されました。
だが、実際の数字と構造を照らし合わせていくと、それは単なる“失敗”ではなく、リスクを織り込み済みで設計された興行構造だったことが見えてきます。
ここでは、経費の実態、収益ライン、そして「ガラガラ」とされた背景を整理しながら、損失の実像に迫ります。
PayPayドーム公演の基本経費:1公演で約5〜8億円のコスト
福岡PayPayドームの1公演にかかる費用は、会場レンタル、ステージ設営、照明・音響、人件費、映像制作、宣伝費、出演料などを含めておおよそ5億〜7.8億円規模に達します。
知恵袋上の複数の回答でも「ドーム公演1本で最低でも数億円」という見積もりが共通しており、チケット代や物販だけで回収するのは極めて難しい構造であることがわかります。
PayPayドームの会場利用料だけでも設営・撤去にそれぞれ約600万円、開催日のレンタル料が約1200万円。さらに警備・照明・清掃・PAなどのオペレーション費を加えると、単にドームを借りるだけで6000万円近い出費となります。
この時点で、採算を取るにはチケット単価と動員が極めて重要になります。
チケット単価・販売枚数から見える収益ライン
今回のチケット価格はおよそ1枚あたり9900円前後。ドームの収容人数は最大約4万人とされます。
仮に満員となれば単純計算で約4億円のチケット収入が見込まれます。これにグッズ販売や配信チケットなどを加えれば、8億円規模の総収益も理論上は成立します。
しかし、実際はSNS上で「客席の2〜3割しか埋まっていなかった」との報告が目立ち、動員は約1万人前後と推定されます。
つまり、単純な計算でもチケット収入は1億円弱〜1.5億円程度にとどまった可能性が高い。そこに物販収益(推定5千万円前後)を加えても、全体の売上は2億円台。経費との差を考えれば、数億円規模の赤字は避けられなかったと見られます。
一方で、一部では「配信収益やスポンサー契約で黒字圏に戻った可能性もある」との見方もあり、実際の損益はまだ断定できません。
“ガラガラ”と言われた客席の真相と損益のバランス
SNSで「ガラガラ」と言われた理由は、単なる人数だけではありません。
観客の配置、撮影アングル、そして照明演出の“抜け感”が、視覚的に「空席が目立つ印象」を強めたと分析できます。
また、ドーム全体を使う演出設計のため、実際よりも空間が広く見えてしまう現象も重なりました。
ある回答者は「
チケット代と物販を合わせればギリギリ赤字ではなかったか、多少の利益が出た可能性もある
」と指摘しています。つまり、「ガラガラ=大失敗」というわけではなく、“赤字前提の完結ライブ”という選択肢を取ったとも考えられるのです。
ビジネス的に見れば損失。だが、興行的・象徴的には、それを“代償”として支払う覚悟を内包していた――そう考えると、この公演の意味は単なる赤字計算の外側にあります。
最後のドーム公演で見せたものは、損得ではなく「物語の終わりを自分たちで選んだ」というメッセージ。それこそが、このライブの“収益”だったのかもしれません。
2.5万枚販売は本当か?チケット枚数のズレとSNSでの誤解
レペゼンの解散ライブをめぐって最も混乱を生んだのが、YouTube配信で語られた「チケット2.5万枚売れた」という数字でした。
この発言を信じたファンの間では、「それなら空席は説明がつかない」「残りのチケットはどこに消えたのか?」といった疑念が一気に拡散しました。
ここでは、その“2.5万枚”という数字の真偽と、なぜSNSで「ガラガラ」との印象が広まったのかを整理します。
YouTube配信での「2.5万枚」発言の背景
知恵袋の投稿によると、ライブ直前のYouTube配信でDJ社長が「約2万5千枚のチケットが売れた」と発言したことがきっかけでした。
この数字は公式発表ではなく、あくまで本人の口から出た推定値。さらに、オンライン配信チケットや関係者席を含んでいた可能性も高く、実際の来場者数とは必ずしも一致していなかったと考えられます。
ライブ興行では、宣伝目的で販売予定枚数を「販売済み」と表現するケースもあり、“売れた”と“入った”の境界が曖昧になりやすいのが実情です。
そのため、「2.5万枚発言」自体が誤りというよりも、ファンの受け取り方と現場の現実のズレが問題を拡大させたと言えます。
実際の動員は約1万人?空席に関する現地証言と写真
複数の来場者がSNSや知恵袋で「1万人もいなかった気がする」と証言しています。
PayPayドームの収容人数は約4万人。SNSで拡散された画像を分析すると、観客は全体の2〜3割、つまり1万人前後にとどまっていたと見られます。
空席を隠すためにステージ演出で照明を落としたり、アリーナ席を前方中心に寄せる配置が取られたと推測されます。
視覚的にはスカスカに見えたとしても、実際には「集中配置型」の構成でライブを成立させていた可能性が高いのです。
それでも「空席が目立つ」との印象が残ったのは、かつてのレペゼンが“満員ドーム”という象徴的イメージで語られていたからです。
その比較が、現実よりも強い「落差感情」を呼び起こしたといえます。
チケット購入者=来場者ではない構造(転売・記念買いの影響)
さらに見逃せないのは、チケットを「購入したが来場していない」層の存在です。
知恵袋の回答では「ファンが余分に買ってもおかしくない」という指摘があり、“応援購入”や“記念買い”が相当数発生していたと見られます。
レペゼンのファン文化では、ライブ参加だけでなく「購入で支える」スタイルが定着しており、その結果、販売枚数と実入場数に大きなギャップが生じた可能性があります。
加えて、転売・譲渡・無効化されたチケットも一定数発生しており、これらが「どこに消えたのか?」という誤解を助長しました。
つまり、「2.5万枚売れた」という言葉は部分的には事実でも、興行の“熱量”を正確に示す数字ではなかったのです。
SNSが炎上構造を作るとき、最も拡散されやすいのは「真実よりも矛盾」です。数字のズレが“裏切り”の象徴として消費されたとき、ファン心理は共感から疑念へと反転していきました。
そしてこのズレこそが、ライブ後も議論が続く最大の火種になったのです。
なぜ“ガラガラ”が強調されたのか:視覚と感情の乖離
レペゼンの解散ライブが終わった直後、SNSのタイムラインを埋め尽くしたのは「ガラガラ」「スカスカだった」という言葉でした。
だが、その“印象”がどのように生まれたのかを分解すると、そこには単なる観客数の問題ではなく、感情と視覚がズレてしまった構造的な理由が浮かび上がります。
空席が象徴として語られたのは、「満員ドーム」という理想を知っていた人たちの“期待の反動”でもあったのです。
「満員であること」への期待と現実の差
かつてのレペゼン地球は、SNSでもYouTubeでも「勢い」と「熱狂」を象徴する存在でした。
だからこそ、ファンもアンチも含めて“ドームを埋める男たち”というイメージを共有していたのです。
ところが、解散ライブで目にしたのは、空席が目立つスタンド席。観客の歓声よりも照明の抜けが印象に残る映像。
この視覚的なギャップが、数字以上に「終わった感」を増幅させました。
ファンが失望したのは、動員の減少そのものではなく、彼らの象徴であった“満員神話”が崩れたことだったのです。
つまり、“ガラガラ”という言葉は、客席の状態を指したのではなく、かつての熱狂との距離を指した比喩として拡散されていったのです。
空席が象徴に変わるとき、ファン心理はどう反転するのか
空席は、ライブ業界において最も強い「沈黙のメッセージ」です。
それは単に人がいないという事実ではなく、“期待が満たされなかった”という集団の感情の可視化です。
かつて「レペゼンは嫌いだけど勢いは認める」と言われた彼らが、今度は「もう時代が終わった」と言われる立場になったとき、空席はその“象徴”として消費されました。
炎上や失速を語るとき、数字よりも画像が拡散される理由はそこにあります。
視覚的な“欠落”は、どんな言葉よりも速く感情を伝播させる。
そして人々は、空席を見て「終わり」を感じるようにできているのです。
この現象は、本人たちの努力やライブ内容とは無関係に発生します。「何が起こったか」よりも「どう見えたか」が語られる。これが現代のバズと炎上の法則です。
数字では測れない“興行の温度差”
SNSでの「ガラガラ」論争がここまで加熱したのは、レペゼンのライブが数字ではなく“熱量”で評価されてきたからです。
視聴者はチケットの販売枚数よりも、ステージと客席の“呼吸の一致”を求めていました。
たとえ1万人が入っていたとしても、4万人の空間の中では冷たく見える。
その温度差こそが、「もうあの頃のレペゼンじゃない」という感情を生んだのです。
言い換えれば、“数字では証明できない興行の成功”をずっと積み上げてきたグループだからこそ、今回は数字に縛られた評価に苦しむ形になったとも言えます。
このズレは、ただの集客の話ではなく、アーティストとファンの“信頼の温度”の乖離です。
そしてこの温度差をどう埋めるかが、レペゼンの物語を次に語る者たちに託されたテーマなのかもしれません。
それでも“最後にドームを選んだ”理由
「ガラガラ」「赤字」と言われながらも、彼らが最終公演の舞台に選んだのは地方ホールでもアリーナでもなく、福岡PayPayドームでした。
冷静に考えれば、採算を重視するならもっと小規模な会場を選ぶ方が合理的です。
それでも、彼らは最初に夢を見た場所に戻り、終わりをそこに刻むことを選んだ。この決断の裏には、“数字では測れない”信念と象徴性がありました。
解散の舞台にドームを選ぶ象徴的意味
レペゼンが初めてドームに立ったのは2019年。無名からのし上がり、YouTubeと音楽を横断しながら「ネット発アーティストでもドームを埋められる」という前例を作りました。
その原点に戻るように、解散の地もまた同じ福岡ドーム。
彼らにとってドームは単なる会場ではなく、“自分たちの物語の起点と終点”を象徴する場所だったのです。
たとえ赤字でも、たとえ満員でなくても、「ドームで終わる」という演出そのものが、観客ではなく“時代”に向けたメッセージだったのでしょう。
観客数よりも、物語の完全性を優先した終幕。その意図を読み取ると、この公演は敗北ではなく、“幕引きの美学”として理解することができます。
収益より“完結”を優先した可能性
知恵袋の回答の中には「数億の赤字でもやる覚悟があったはず」という指摘がありました。
実際、ドーム公演にはスポンサー契約や配信収益が存在し、完全な自己負担ではないにせよ、利益を最大化する構造ではありません。
むしろ、“収益を捨てて完結を取る”という選択をした点に、このライブの本質があったと言えます。
一般的なアーティストが解散ライブを行う場合、収益・DVD化・グッズ展開などを含めた“延命型”の設計が多い。
しかしレペゼンは、活動の終わりを明確に線引きし、ドームという巨大な箱に「終わり」を閉じ込めることを選びました。
これは、YouTubeという拡散の海で常に注目を奪い合ってきた彼らが、最後に選んだ“沈黙への帰還”でもありました。
演出と構成に見えた「最後の意地」
ライブ内容を見た観客の中には、「ステージ演出がいつもより静かだった」との声もあります。
それは予算の制約ではなく、意図的な抑制だったのかもしれません。
DJ社長を中心とするメンバーたちは、MCで過去の騒動や仲間への感謝を口にしながらも、涙や謝罪に逃げることはしませんでした。
むしろ、“笑って終わる”という彼ららしい終幕を徹底したのです。
これを「無理に明るく振る舞った」と受け取るか、「最後までエンタメを貫いた」と見るかで、ライブの印象はまったく変わります。
ただ確かなのは、彼らが“惨敗”を演じることを拒み、“自分たちの形で終わる”ことを最優先したということです。
それは数字ではなく、意地の興行。
空席のドームを背に、堂々と笑っていた姿は、ある意味で最もレペゼンらしい「敗者の勝利」でした。
だからこのライブは、損失ではなく宣言。
「俺たちは終わる。でも、終わり方は自分たちで選ぶ」――その一言が、赤字の帳尻を超えるほどの価値を残したのです。
ファンが抱いた違和感:「あの頃のレペゼン」との距離
レペゼンの解散ライブが終わった後、SNSには「泣いた」「感動した」という声と同じくらい、「なんか違った」「あの頃の勢いがなかった」という感想が並びました。
そこには単なるライブの評価ではなく、“かつてのレペゼン像”とのズレが滲んでいます。
ファンが感じた違和感は、パフォーマンスの質ではなく、「レペゼンとは何だったのか?」という根本的な問いに触れるものでした。
全盛期との比較が生む“失望の炎上”
全盛期のレペゼン地球は、SNSの象徴そのものでした。無茶・仲間・勢い・下ネタ・成功神話――それらが混ざり合って、視聴者の「代わりに夢を見てくれる存在」でした。
だからこそ、解散ライブの“静けさ”はファンにとって、かつての熱狂とのギャップを突きつけるものになった。
観客席の空白よりも、ステージ上の“抑えたトーン”が違和感を生んだのです。
SNSでは「最後なのにあっさりしていた」「昔みたいにバカ騒ぎしてほしかった」という声が多く見られました。
しかしこの“物足りなさ”こそが、彼らが過去の自己演出を超えようとした証拠でもありました。
彼らは、かつての炎上芸を繰り返すよりも、終わり方そのものを作品化する道を選んだのです。
好感度で支えられた均衡の崩壊
レペゼンが築いてきた人気は、決して「音楽の質」だけでできていたわけではありません。
ファンとの距離感、SNSでの親密さ、ストレートな言葉。
それらが“好感度”という見えない均衡を支えていました。
しかし、暴露騒動やメンバー間の確執、ビジネス的な再結成などが続く中で、その均衡は少しずつ揺らいでいたのです。
解散ライブは、その歪みが表面化した瞬間でもありました。
かつては「無敵」に見えたチームが、普通の人間の終わり方をした――そのリアリティが、ファンの中で“裏切り”のように映ったのでしょう。
「期待」と「現実」の差が広がったとき、ファンの熱は熱狂から冷静へ、そして静かな失望へと変わります。
それは炎上ではなく、信頼が冷める音でした。
“終わり方”にファンが求めていた誠実さ
ファンが本当に求めていたのは、ドームを満員にすることではなく、「レペゼンらしい終わり方」だったはずです。
DJ社長の涙でも、派手な演出でもなく、“本音で語る姿”を見たかった人が多かった。
しかしライブでは、笑顔で締めくくられ、深い説明や総括はほとんどありませんでした。
その選択を「潔い」と受け取る人もいれば、「逃げた」と感じる人もいた。
この分岐が、ライブ後の議論を長引かせた要因です。
観客の多くは「最後のレペゼン」を見に行ったのではなく、“自分の青春の終わり”を確認しに行ったのです。
だからこそ、彼らが笑って終わった瞬間、多くの人が置いていかれたような喪失感を覚えた。
解散とは、アーティストの終わりではなく、ファン一人ひとりの物語の終幕でもあるのです。
そしてその幕が下りた瞬間、「あの頃のレペゼン」は、永遠に届かない場所へと行ってしまったのかもしれません。
レペゼン解散ライブと損失の実態をめぐるまとめ
レペゼンの解散ライブは、単なる「ドームが埋まらなかった公演」ではありませんでした。
そこには、数字では測れない信念、終わり方への哲学、そしてファンとの関係性の“最後の答え合わせ”がありました。
赤字であったとしても、それは失敗ではなく、物語を完結させるためのコストだったと見るべきです。
数字以上に問われたのは「終幕の物語性」
レペゼンのライブが常に注目を集めてきた理由は、音楽そのものよりも「ストーリー性」にありました。
“無名からドームへ”“炎上から復活へ”“仲間と夢を叶える”――そうした構造が、SNS世代の共感を支えていたのです。
その彼らが最後に見せたのは、「終わりもまた、物語の一部である」という姿勢でした。
ファンの視点では「物足りなかった」かもしれません。
でも彼らは、もう一度同じ熱狂を演じるより、“幕を閉じる勇気”を選んだ。
だからこのライブは、エンタメの終わり方として異例の静けさをまとっていたのです。
赤字でも残した“象徴的価値”とファンへのメッセージ
たとえ数億円の損失があったとしても、彼らが選んだ「ドームで終わる」という決断は、それ自体が強烈なメッセージでした。
興行的な成功よりも、象徴的な「完結」を優先する姿勢――それは、どんなブランド戦略や再生回数よりも強い意味を持ちます。
ファンにとってこの公演は、“終わり”ではなく“卒業式”のようなものでした。
満員の熱狂を再現することよりも、「どんな姿で終わるか」を選ぶこと。
それこそが、最後までレペゼンが貫いたエンタメ哲学だったのです。
DJ社長は以前こう語っていました。
「成功も失敗も、俺たちの物語の一部やけん。」
この言葉は、まさにこのライブの本質を言い当てています。
損失の先にある、音楽活動と信頼のリセット
解散ライブをもって一つの時代が終わったのは確かです。
しかし、終わりは同時に“再生の余白”でもあります。
彼らが次にどんな形で活動を再開するかはまだ不明ですが、今回の赤字は信頼を再構築するための投資と見ることもできます。
満員のドームよりも、もう一度“信じてもらう”ことの方が難しい。
そのことを痛感した今の彼らは、過去の延長ではなく、“ゼロからの信頼”を作り直すフェーズに入ったのかもしれません。
このライブが損失で終わるのか、それとも再生の序章になるのか――それは彼らの次の一歩で決まります。
少なくとも、空席のドームで終わったあの夜、レペゼンは「観客の数では測れないエンディング」を自分たちの手で描いていた。
そしてその静けさこそが、最も彼ららしい“本音の証明”だったのではないでしょうか。
- レペゼン解散ライブは赤字覚悟で挑んだ「完結の興行」だった
- チケット2.5万枚発言は配信・記念購入を含む可能性が高く、実動員は約1万人前後
- “ガラガラ”という印象は視覚効果と期待の反動によるもの
- 赤字は損失ではなく、物語を完結させるためのコストと考えられる
- ドームを選んだのは、始まりと終わりを同じ場所で閉じる象徴的意味
- ファンが感じた違和感は「かつての熱狂」との距離によるもの
- ライブの静けさは敗北ではなく、“自分たちの形で終わる”という意地の表現
- 損失よりも「終幕の物語性」と信頼の再構築がテーマとなった
- 空席のドームで終わった夜こそ、レペゼンらしい本音の証明だった
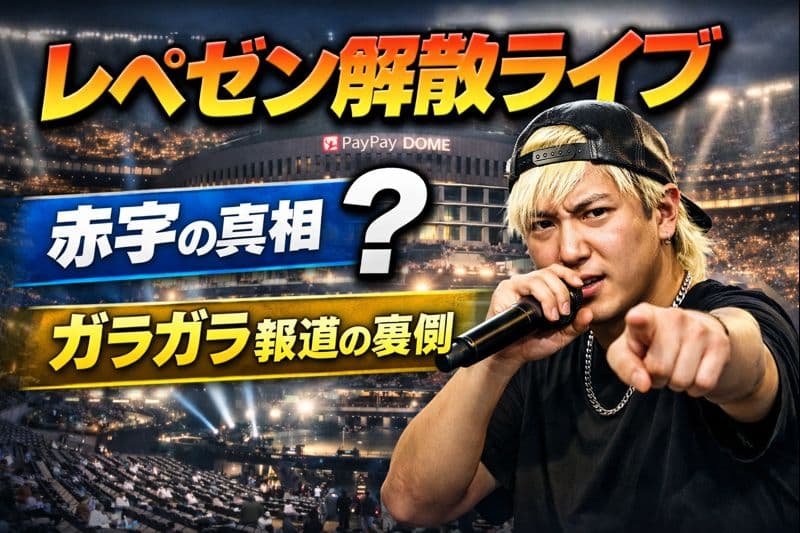


コメント